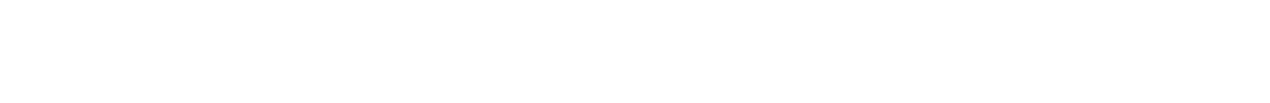建設業許可採番ルール

建設業許可の業種区分は29種類
建設工事の種類は建設業法上で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受ける必要があります。
建設業法における工事の種類は、大きく分けて以下の2つに分類されます。
1. 一式工事:2種類
- 土木一式工事: 土木工作物(道路、橋、トンネルなど)を総合的に建設する工事です。
- 建築一式工事: 建築物(住宅、ビルなど)を総合的に建設する工事です。
2. 専門工事:27種類
- 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、 шахт工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、解体工事、清掃施設工事などがあります。
これらの工事の種類ごとに、建設業許可を取得する必要があります。
建設業の許可番号における採番ルールは、日本の建設業法に基づいており、許可を受けた企業に対して付与される番号は、企業が取り扱う業種やその許可の種類に応じて分類されます。代表的な番号の形式について説明します。
1. 許可番号の形式
建設業の許可番号は、一般的に以下の形式で表されます:
- 番号の例: 〇〇-〇〇-〇〇
ここで、各部分が示す内容は以下の通りです:
2. 採番ルールの構成
- 最初の数字(例:7)
- 最初の数字は、許可を受けた年度を表しています。例えば「7」となっている場合、平成7年度(1995年度)に許可されたことを意味します。
- 業種コード(例:般)
- 次の部分は、業種コードを表します。主に以下の2種類に分かれます:
- 般(一般建設業):一般的な建設業者の許可を意味します。多くの建設業者はこの許可を持ちます。建設業者が特定の工事を請け負う場合、一般建設業の許可を得ている必要があります。
- 特(特定建設業):特定建設業の許可を示します。この許可を持つ業者は、特定の金額以上の工事を請け負うことができ、公共工事や大規模な建設工事を担当します。
- 次の部分は、業種コードを表します。主に以下の2種類に分かれます:
- 番号(例:1)
- 最後の部分は、その建設業者の許可番号を示します。番号は順番に付与され、例えば「1」とは、その年度における最初の許可業者であったことを意味します。
3. 具体例
以下のような許可番号が考えられます:
- 7-般-00123
- 「7」は平成7年度に許可されたことを示し、「般」は一般建設業の許可で、「00123」はその年度における123番目の許可業者であることを示します。
- 10-特-00045
- 「10」は平成10年度に許可されたことを示し、「特」は特定建設業の許可で、「00045」はその年度における45番目の許可業者であることを示します。
4. 業種コード(一般・特定)
建設業には、以下のように複数の業種があり、それに対応する業種コードが存在します:
- 般:一般建設業
- 特:特定建設業
- 管:管工事業
- 電:電気工事業
- 土:土木工事業
- 舗:舗装工事業
- 造:造園工事業
- ほか:建設業法に基づくさまざまな業種(解体工事、鉄道工事など)
建設業の許可番号の採番ルールは、最初の数字が許可された年度、次に業種の分類(一般建設業や特定建設業など)を示し、最後にその年度内での許可番号を表します。このように、許可番号からその業者の許可状況や業種、許可された年度が一目でわかる仕組みになっています。
例ーTANAAKKファシリティーズ
「東京都知事許可(般一7)第160003号 管工事業」はTANAAKKファシリティーズの許可番号です。
1. 東京都知事許可
- 東京都知事許可は、その建設業者が東京都において建設業の許可を得ていることを意味します。建設業者は、地域ごとに都道府県知事または国土交通大臣から許可を受ける必要があります。東京都知事許可ということは、東京都内で営業している建設業者であり、東京都に対して許可を得ているということです。
2. (般一7)
- 般:これは、一般建設業の許可を示しています。一般建設業の許可を持つ業者は、主に下請けを使わず、自社の能力で建設工事を行うことができます。
- 7:これは、許可を受けた年度を示しています。この「7」は、**令和7年度(2025年度)**に許可を受けたことを意味します。具体的には、2025年4月1日から2026年3月31日までの間に許可を受けたことを示します。
3. 第160003号
- 第160003号:これは、その年度における許可業者の番号を示します。「160003号」ということは、東京都で160003番目の建設業者として許可を受けたことを意味します。
結論
東京都知事許可(般一7)第160003号は、次のように解釈できます:
- 東京都で営業している建設業者
- 一般建設業の許可を受けている業者
- 令和7年度(2025年度)に許可を受けた業者
- 160003番目の許可業者
例 他社の番号について
主に年商1兆円以上の建設業の許可番号は以下の通りです。
| 許可主体 | 番号 | 企業名 | 本店 |
| 関東地方整備局 | 第000300号 | 大成建設(株) | 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
| 関東地方整備局 | 第002100号 | 鹿島建設(株) | 東京都港区元赤坂1-3-1 |
| 関東地方整備局 | 第002655号 | 前田建設工業(株) | 東京都千代田区富士見2-10-2 |
| 近畿地方整備局 | 第002744号 | (株)竹中工務店 | 大阪府大阪市中央区本町4-1-13 |
| 関東地方整備局 | 第003000号 | (株)大林組 | 東京都港区港南2-15-2 |
| 関東地方整備局 | 第003200号 | 清水建設(株) | 東京都中央区京橋2-16-1 |
| 関東地方整備局 | 第004237号 | 住友林業(株) | 東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館 |
| 近畿地方整備局 | 第005279号 | 大和ハウス工業(株) | 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 |
| 近畿地方整備局 | 第005295号 | 積水ハウス(株) | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 |
| 関東地方整備局 | 第007371号 | 大東建託(株) | 東京都港区港南2-16-1 |
建設業の許可において、地方整備局と自治体(都道府県)の許可には違いがあります。
1. 地方整備局の許可
- 地方整備局は、国土交通省の下にある地方の行政機関です。地方整備局は、主に公共工事や大規模な建設工事を担当します。
- 管轄: 各地域における国土交通省の地方支局が担当します。地方整備局は、特に国や大規模公共事業(例えば、道路建設や橋梁の建設など)の許可を行います。
- 許可の範囲: 地方整備局が発行する許可は、大規模なインフラ工事や国の公共工事を主に対象とするため、一定規模以上の工事に対応できる業者が対象になります。
- 許可番号: 地方整備局から発行される許可番号は、都道府県の許可番号とは別に設定され、番号に地域や管轄が反映されます。
2. 自治体の許可(都道府県知事許可)
- 都道府県知事許可は、各都道府県が管轄する建設業者への許可を指します。自治体が発行する許可は、主に地域内での建設工事や公共工事を対象にします。
- 管轄: 各都道府県(または政令市)の知事が、都道府県内で営業する建設業者に対して許可を出します。都道府県や市の規模によって、許可を発行する範囲が異なります。
- 許可の範囲: 都道府県知事許可は、主に地方自治体が発注する工事(例えば、地方道路の舗装工事や市営住宅の建設など)を対象にしています。これにより、自治体内での建設業者が仕事を請け負う際に必要な許可となります。
- 許可番号: 都道府県知事許可は、その都道府県内でのみ有効であり、番号はその都道府県ごとに付与されます。番号はその都道府県内で順番に付与され、都道府県ごとに管理されます。
3. 主な違い
| 項目 | 地方整備局許可 | 自治体(都道府県)許可 |
|---|---|---|
| 発行者 | 国土交通省の地方整備局 | 都道府県知事 |
| 管轄範囲 | 主に国の大規模な公共工事(道路、橋梁、空港など) | 地方自治体内での工事(市町村の施設、道路等) |
| 対象となる工事 | 大規模なインフラ工事や国の工事 | 地方自治体の公共事業、地域内での建設工事 |
| 許可番号の違い | 地方整備局発行の許可番号(国の工事向け) | 都道府県ごとに発行される許可番号 |
| 主な許可対象業者 | 全国規模で大規模な工事を請け負う業者 | 地元または地域の建設業者 |
4. 具体例
- 地方整備局の許可を受けた業者は、例えば高速道路の建設や国道の改修工事など、国の大規模なインフラ工事を請け負うことができます。
- 自治体の許可を受けた業者は、地域内での公共施設建設(市役所の建設や地方の道路工事など)を主に請け負います。
結論
地方整備局の許可は、主に国の大規模公共事業に関連する許可であり、自治体(都道府県)知事許可は、地域内で行われる公共工事を対象にした許可です。大規模な国の工事を請け負うためには地方整備局の許可が、地域の小規模な工事を請け負うためには自治体の許可が必要となります。
建設業許可なし、一般、特定の違い
軽微な建設⼯事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営もうとする者は、元請・下請を問わず⼀般建設業の許可を受けなければなりません。また、発注者から直接⼯事を請け負い、かつ4,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上を下請契約して⼯事を施⼯する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法 第3条・第15条参照)
建設業許可がない場合、つまり、建設業許可を取得していない場合に受けられる最大金額については、建設業法に基づいて制限があります。具体的には、建設業許可を持っていない業者が受けられる工事の金額には以下のような制限があります。
●発注者から請け負う額に制限はありません。
→ 必要な許可が、“特定”であるか、“⼀般”であるかは、下請契約の総額によって決まります。
●受注する⼯事の規模の⼤⼩は関係ありません。
→ ⽐較的規模の⼤きい⼯事を元請として受注した場合でも、その全部を元請にて⾃社施⼯するか、下請発注額が4,500万円未満であれば、⼀般建設業の許可で足ります。
●「特定建設業の許可が必要」になるのは、元請業者に対してのみです。
→ ⼀次下請以下として契約されている建設業者については、このような制限はありません。
※⼀次下請業者が⼆次下請業者に対して発注する額に制限はありません。
1. 建設業法違反の罰則
建設業法では、建設業を営むためには建設業許可が必要であると定めています。許可を持っていない業者が工事を請け負うことは法的に禁止されており、違反した場合には罰則が適用される可能性があります。
罰則の内容
- 懲役刑または罰金:許可を持たずに建設業を営んだ場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる場合があります
- 営業停止命令:許可を持たずに建設業を営んだ場合、事業の停止を命じられることもあります。行政からの指導を受け、改善が見込めない場合は営業停止処分が下されることもあります。
2. 違法に工事を請け負った場合の責任
許可なしで工事を請け負った場合、法律に基づき以下の責任が発生します:
- 契約無効:許可なしで受注した工事契約は、原則として無効と見なされます。工事契約が無効となった場合、その後の支払い義務や契約内容に関して法律的に争いが生じる可能性があります。
- 工事の質や安全:許可なしで工事を行った場合、建設業法に基づく安全基準や品質基準に従わない可能性があり、施工不良や安全問題が生じた場合、さらに法的責任が発生することになります。
3. 元請け業者への影響
元請け業者が、許可を持たない業者と契約を結んだ場合、元請け業者にも責任が及ぶことがあります。元請け業者が許可なしの業者を選定し、契約を結んだ場合、その契約が無効になったり、法的な問題が発生したりする可能性があります。また、元請け業者に対しても行政指導や処分が行われることがあります。
4. 許可なしで下請け業者になる場合
下請け業者も、上記と同じく許可なしで500万円以上の工事を請け負うことはできません。もし、下請け業者が許可なしで工事を請け負った場合、元請け業者に損害が及ぶ可能性があります。また、元請けが許可を持っていない業者を下請けに選んだ場合、その契約は無効となることがあります。