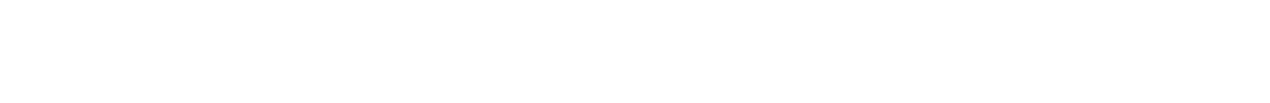ユーザー志向型ファシリティマネジメントの将来性|IT業界のメタファー

「カスタマータッチポイントが多い企業は、歴史的にマーケットオーナーとしてバリューチェーンを独占する」
これはIT業界で証明されてきた法則であり、デジタル化が進みづらい業界でも、そう遠くない未来に適用される可能性が極めて高い。
ユーザのタッチポイントを企業経営の至上原理とし、業界の伝統や法令、慣習を含む様々なコストを抜本的にゼロから見直し、ユーザーのアテンション(意思)を中心として(Attention Based Assembly™)、最小エネルギーで実現する(Least Action Principles™)。この真理を中心として産業を見直す姿勢を基盤として、主に小売、製造、メディアを中心として、テクノロジーが既存産業を一気にひっくり返した。ファシリティマネジメント業界でも適用される可能性が極めて高い。
ファシリティマネジメント業界は、IT業界が辿った進化の道と似た変革を迎える可能性があります。以下に、IT業界のメタファーを活用しながら、ユーザーセントリックにあらゆるコストが最適化されていくであろうファシリティマネジメント業界の未来像を予測します。
1. ファシリティマネジメントの「エンジニア」は誰か?
メタファー: 「IT業界におけるエンジニア ≒ ファシリティ業界における保守運用者」
クラウド時代以前のエンジニアと同様に、現在のファシリティマネジメント業界では、保守運用者(メンテナンススタッフ、設備管理者、ビルマネージャー)の役割が過小評価されています。しかし、実際にはこの人々が、施設の維持管理、エネルギー最適化、ユーザー対応を通じて、建物の価値と収益性を左右しています。
2. ファシリティマネジメント業界における「クラウド化」とは?
メタファー: 「オンプレミスITからクラウドへ移行 ≒ 物理的な施設管理からデータ駆動型管理へ」
従来のファシリティマネジメントは、物理的なメンテナンスが中心であり、建物ごとに管理が行われていました。しかし、IoTセンサー、スマートビルディング、デジタルツイン技術の発展により、データをクラウドに集約し、AIが最適な運用を判断する「クラウド型ファシリティマネジメント」へと移行が進んでいます。
- 従来: 物理的な点検、手動報告、経験則によるメンテナンス
- 未来: IoT+AIによる予測メンテナンス、リアルタイムのオペレーション、エネルギー最適化
→ Microsoft Azureが企業のITインフラをクラウド化したように、スマートファシリティ管理プラットフォームが、建物のインフラをデジタル化する。
3. 「CIO/CSOの地位の低さ」と「ファシリティマネジメントの意思決定権」
メタファー: 「かつてCIO/CSOの影響力が低かったように、ファシリティ管理者の地位も高くはない。しかし、今後は変化する。」
従来、企業の施設管理者は、IT部門と同じように、戦略的な意思決定に関与せず、単なる維持管理業務の一部として扱われていました。しかし、データ駆動型の施設管理が進むにつれて、企業の経営戦略に影響を与えるポジションへと変化していく可能性があります。
- 従来のIT部門: CIO(Chief Information Officer)は、企業の主要意思決定にほとんど関与していなかったが、クラウド時代の到来で戦略的な役割を担うようになった。
- 従来のファシリティ管理: 設備管理者やFMマネージャーは、施設の修繕や維持管理を担当するだけだったが、エネルギーコスト削減、ESG対応、スマートビルディングの導入が進むことで、企業の経営戦略に関与するようになる。
→ CIO/CSOが企業経営の中核になったように、「ファシリティ戦略責任者(CFO = Chief Facility Officer)」が、アセットマネージャーとして経営の中核に入る時代が来る。
4. オープンソースコミュニティのメタファー
メタファー: 「エンジニアのオープンソースコミュニティ ≒ ファシリティマネジメントのオープンデータネットワーク」
クラウド事業者は、オープンソースコミュニティを活用することで、エンジニアの労働力を無料で活用しつつ、エコシステムを拡大しました。同様に、ファシリティマネジメント業界でも、施設管理のノウハウやデータを共有するオープンプラットフォームが登場する可能性があります。
- IoTデバイスやセンサーデータの共有
- 不動産オーナーや管理会社が、メンテナンスデータを相互活用
- スマートビルディング管理プラットフォームの標準化
→ オープンデータ化が進めば、ファシリティマネジメント業界の「GitHub」のようなプラットフォームが生まれるかもしれない。
5. ボトムアップ営業の可能性
メタファー: 「トップ営業からボトム営業へ ≒ ファシリティマネジメントの購買決定権が変わる」
かつて、ITソリューションは経営層向けのトップ営業が主流でした。しかし、クラウド時代になり、実際に技術を扱うエンジニアが購買意思決定に関わるようになったことで、AWSやAzureは成功しました。
同様に、ファシリティマネジメント業界でも、購買意思決定者がトップダウンからボトムアップへと変化する可能性があります。
- 従来: 企業の経営層や不動産オーナーが大規模な管理契約を結ぶ。
- 未来: 実際に建物を管理する現場のファシリティマネージャーが、使いやすいデジタルツール(SaaS)を選択する権利を持つ。
→ SaaS型のファシリティ管理ツールが普及し、現場担当者が自ら導入を決定する時代になる。
ファシリティマネジメント業界の未来
- 「エンジニアの時代」同様に、「ファシリティ管理者の時代」が到来する。
- 保守運用者が過小評価されていたが、データとテクノロジーの活用で地位が向上。
- クラウド化とデータ活用が、施設管理の新たな標準となる。
- IoT+AI+クラウドにより、リアルタイムの施設管理が可能に。
- ファシリティマネジメントの戦略的価値が高まり、新しい経営ポジション(CFO = Chief Facility Officer)が生まれる。
- オープンソースのように、データ共有とオープンプラットフォームが業界の進化を加速させる。
- 「ボトムアップ営業」によるSaaSファシリティ管理ツールの普及が起こる。
→ 結論として、ファシリティマネジメント業界は「クラウド化・データ化・分散化」することで、MicrosoftやAWSがIT業界を変えたように、革新の時代を迎える。